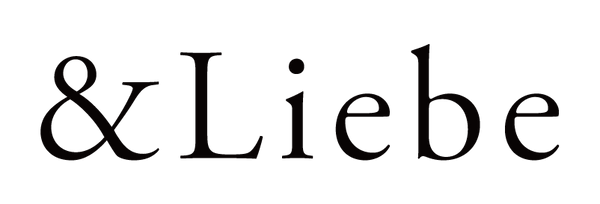時間と手間が生み出す、
唯一無二の革
工場見学を通して強く感じたのは、栃木レザーの革は、単なる「素材」ではなく、手間と時間、そして自然の力が育んだ“作品”のような存在です。
他のレザーとどこが違うのか?それは、細部にまで宿る「こだわり」にあります。
■ 革本来の風合いを生かす
「フルベジタブルタンニンレザー」

栃木レザーで使われているのは、“フルベジタブルタンニンレザー”。
これは、「ミモザ」の樹皮から抽出された天然の植物タンニンのみを使って鞣された革のことです。
化学薬品や有害物質を一切使わず、自然の恵みだけで革を仕上げる製法は、環境にも優しく、革そのものの個性が際立ちます。
この製法の大きな特徴は、使うほどに色艶が深まり、経年変化(エイジング)を楽しめること。
革の油分がじんわりとにじみ出て、持ち主の手に馴染みながら“あなただけの革”へと育っていきます。
■ 生産性よりも「品質」を
優先した手間のかかる製法

通常、多くの皮革製造では生産効率を高めるために、原皮を引き伸ばして加工を始めます。
しかし、栃木レザーでは革の繊維構造を壊さないため、無理な引き伸ばしは行いません。
この丁寧さが、コシのある、長く使える革を生む理由の一つです。
さらに、脱毛工程でも一般的な回転ドラムではなく、5段階の石灰濃度に分けたピット槽で、時間をかけてゆっくり処理。
この工程には、通常の5倍以上の時間がかかりますが、皮に余計な負担や傷を与えないという目的のもと、昔ながらの方法を守り続けています。
■ 断面や傷跡にまで現れる
「本物の証」

こうしたこだわりは、革の裁断面にも現れます。
繊維が潰れた革では断面がボサボサになりますが、栃木レザーの革は繊維が詰まり、断面まで美しい仕上がり。
塗料でごまかすこともなく、牛が生きていたときの傷やシワさえも“味”として残す製法に、革へのリスペクトを感じます。
さらに、染色では「芯通し」と呼ばれる革の芯まで染料を染み込ませる方法を採用。
これにより、表面に傷がついても目立ちにくく、むしろその傷すらも味わいとして経年変化に溶け込んでいくのです。