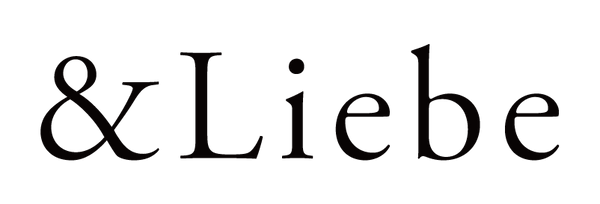ChatGPTの生みの親が
あえて“手書きノート”を選ぶ理由
生成AIのど真ん中を走るサム・アルトマン。
彼は、ChatGPTを開発したOpenAIのCEOであり、シリコンバレーを代表する起業家のひとりです。
最先端の人は最新アプリで全部やっていそうなのに、彼が選ぶのはスパイラル綴じの“ポケットサイズのノートとペン”。
ここに僕は、文具好きとして燃えるポイントが詰まっていると感じました。
「世界には“豪華なノート”がたくさんあるけれど、欲しいとは思わない。スパイラルノートが一番。理由はページを頻繁にちぎれること、机の上でフラットに開くこと。」──How I Write(David Perell)にて。
さらにアルトマンは、ハードカバーでポケットに入るサイズを好み、ユニボールのMicro(0.5)や無印の0.36/0.37ダークブルーといった細軸のボールペンを挙げています。
アナログで書き、リストは頻繁に書き直して見直す──そんな運用が語られています。
そこで今回は、彼がどのようにノートを使いこなし、日々の思考を整理しているのか。
さまざまなインタビューや記事をもとに、そのメモ術を抜粋しながらまとめてみました。
なぜ、小さい「スパイラルノート」なのか?
ノートは大きいサイズの方が、たくさんアイデアを書き出せて便利ですよね。
では、なぜアルトマンはあえて“小さなポケットサイズのノート”を選んでいるのでしょうか。
実はそこには、感性ではなく徹底した機能合理がありました。
1)ポケットに入る携帯性
「いつでも取り出せること」が発想密度を上げる。
一瞬の“引っかかり”を書き逃さないための小型・ハードカバー・ポケットフレンドリーという設計。
手ぶらに近い感覚で持ち歩けることが、習慣を支えているようです。
大きなノートだと持ち歩くのが面倒になって結局書かなくなるので、この携帯性の重視はすごく納得です。
2)180度フラットに開ける
会議でも移動中でも、ノートが勝手に閉じないのは正義。
見開きが“面”として使えるから、図と箇条書きを同時に走らせられます。
パッと開いて、ページを抑える手間がないだけで、思考の集中度が大きく変わりますよね。
僕もノートが勝手に閉じるのって地味にストレスなので、ここはかなり共感しました。
3)「解決=ちぎって捨てる」
アルトマンは書いたメモをちぎれる、複数ページを同時に見るためにスパイラルを推します。
タスクが終わったら丸めて捨てる。
この“破壊”の所作が、頭の中の未解決をゼロに戻す。
完了を“身体で感じられる”点もユニークです。
「解決したらちぎって捨てる」って、すごく快感になりそうだなと感じました。
タスク管理アプリでは得られない達成感ですよね。
4)筆記具は細軸・即応性重視
ペンは“いつでも書けること”がすべて。
Uni-ball MicroやMUJI 0.36/0.37のような細軸・細字は、素早い走り書きに向き、インクの切れも少ない。
細軸はスパイラルのリングに差して一体化しやすいのも実用的です
👆アルトマンはこんな感じで使っています。
手帳バンドやペンホルダーに頼らず“一体化”できるのはスパイラルならではの強みです。
実際、細軸のペンって意外と持ち歩きやすくて、ノートとセットで持つと「書き逃し」がなくなるんですよね。
・「パイロット ボールペン アクロ500」を使っています。
5)3日で1冊を使い切るほど書く
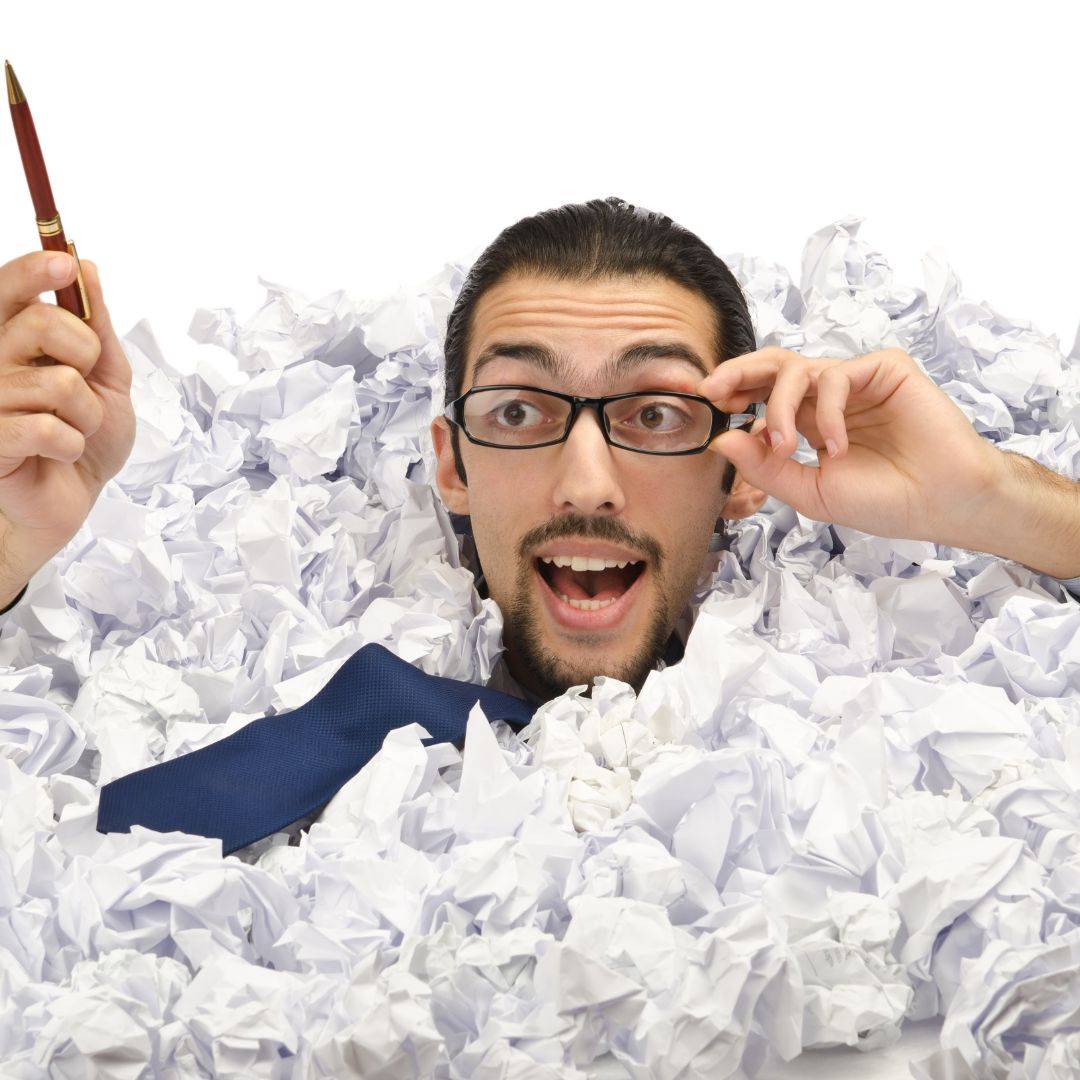
「え、3日で1冊!?」思わず笑ってしまうくらいのペース(笑)
アルトマンは2〜3日でノートを1冊使い切るほど書くそうです。
短いサイクルでノートを回すから、情報が古びず、惰性のメモも残りにくい。
常に“新鮮な頭”で考え続けるための仕組みとして、ノートの使い切りスピードを意識しているのが印象的です。
僕も書きっぱなしのノートが積み重なって後で見返さないことが多いので、この「短期で回す」発想は本当に参考にしたいなと思いました。
手書きは「発想のエンジン」
デジタルに勝る理由
アルトマンの話をまとめてみると、手書きが選ばれているのは「速さ」と「自由さ」。
PCやスマホだと、どうしても“きれいに整える”ことに意識が向きがちですが、紙なら途中でも未完成でもとにかく書き進められる。
走り書きでも形になっていくのが、手書きの一番の強みなんだと思います。

僕もPCに向かうと整えることに時間を取られてしまうので、「とにかく進められる自由さ」は紙ならではだと実感します。
さらにアルトマンは、リストを何度も書き直すそうです。
これは清書するためではなく、そのたびに「今の自分に必要なこと」を見直すため。
言ってみれば、書き直すこと自体が思考の整理になるんですよね。
僕も、これからやりたいことや商品デザインは、必ず紙に書き出しています。
文具にハマると、やっぱり手書きの良さを再認識しますよね。
アルトマンがどんなにAIの最前線を走っていても“紙とペン”を手放さないのは、その心地よさを知っているからだと思います。
僕ら文具好きにとっても、それはすごく共感できる感覚なのかなと思います。
やっぱり手書きって、特別ですよね。
実際に試してみた結果
実際にポケットサイズのスパイラルノートを持ち歩いてみたんですが…
めっちゃ良かったです!!
散歩のときや出先のちょっとした空き時間でもポケットからサッと取り出せて、閃いた瞬間にすぐ書ける。
この「すぐ書ける」だけで、思考の抜け落ちがかなり減りました。
今までは「あっ、いいこと思いついた!」と思っても、後から「なんだっけ?」と悔しい思いをすることが何度もありました。笑
でも紙とペンなら、開いた瞬間に手が動く。
これがすごくいいんです。
さらに、タスクが解決したらページをサッとちぎって捨てられるのも気持ちいい。
完了の瞬間に“紙ごと消える”から、頭の中がスッキリ整理される感覚があります。
チェックマークを入れるより、ずっと達成感があるんですよね。
やってみて初めて分かりましたが、
「持ち歩ける小さなノート」と「ちぎって捨てられる仕組み」。
この組み合わせは本当に素晴らしいと思いました。
「手書きは遅い?」
いえ、最速です
紙って遅いと思われがちですけど、
実は書き始めるまでの初動は一番速いんですよね。
アプリを開いたり、通知に気を取られたりせずに、頭に浮かんだ第一声をそのまま紙に落とせる。これがめちゃくちゃ大きい!
しかもスパイラルノートだと、終わったページをビリッとちぎって捨てられる。
その瞬間の「終わった!」っていう手応えは、チェックボックスに✓を入れるよりもずっと強い気がします。

僕自身、万年筆でじっくり書く時間も大好きなんですけど、アルトマン式の“ポケット・スパイラル×細軸ペン”は、アイデアを捕まえたり段取りを決めたりする時にはほんと無敵。
そして、紙でラフに始められるからこそ、その後にAIで要約したり下書きに広げたりするのもスムーズなんですよね。
アナログとデジタルって対立じゃなくて、それぞれの得意な“速度の分担”で支え合ってるんだなって感じます。
まとめ
アルトマン流「紙とペン」の使い方
✔️ ノートは小型スパイラル
・ポケットに入るサイズ感(B7〜A7くらい)
・ハードカバーで持ち歩きやすい
・2〜3日で1冊を使い切るスピード感
✔️ スパイラルを選ぶ理由
・机に置いても180度フラットに開ける
・終わったページをビリッとちぎって捨てられる
・複数ページを切り離して並べ、俯瞰できる
・リング部分に細軸ペンを差して一体化できる
✔️ ペンは細軸・細字
・ユニボール Micro(0.5)や無印良品 0.36/0.37を愛用
・走り書きに向いていてインク切れが少ない
・細軸なのでノートと一緒に携帯しやすい
✔️ 使い方のスタイル
・思いついたことをその場で即メモ
・タスクやアイデアを同じノートに混在させる
・リストは頻繁に書き直し、“今必要なこと”を常に更新
・終わったらちぎって捨てる → 達成感と頭のリセットにつながる

アルトマンは、最先端のAIを操りながらも、こんなシンプルな紙の習慣を続けています。
だからこそ思考の初動が速く、アイデアを逃さず形にできるのだと思います。
僕も試してみてよかったですし、これからも続けていきます。
皆さんの文具の活用にも、少しでも参考になれば嬉しいです。